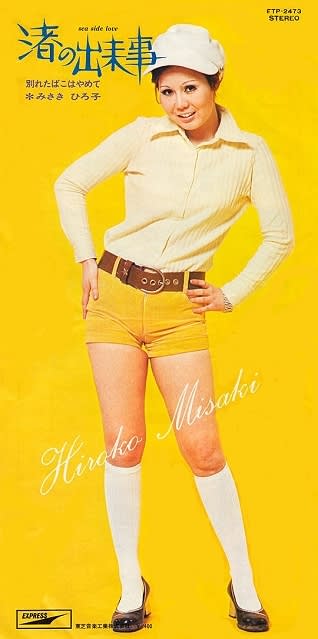■Led Zeppelin 2-CD Deluxe Edition (Atlantic)
![]()
☆Disc-1: Led Zeppelin 1st
01 Good Times Bad Times
02 Babe I'm Gonna Leave You
03 You Shook Me
04 Dazed And Confused / 幻惑されて
05 Your Time Is Gonna Come / 時が来たりて
06 Black Mountain Side
07 Communication Breakdown
08 I Can't Quit You Baby / 君から離れられない
09 How Many More Times
☆Disc-2: Live At The Olympia (1969年10月10日)
01 Good Times Bad Times 〜 Communication Breakdown
02 I Can't Quit You Baby / 君から離れられない
03 Heatbreaker
04 Dazed And Confused / 幻惑されて
05 White Summer 〜 Black Mountain Side
06 You Shook Me
07 Moby Dick
08 How Many More Times
世界中のロックファンを浮かれさせたに違いない最近のアーカイヴ系復刻のひとつが、ゼップの諸作でしょう。
なにしろオリジナルアルバム音源がジミー・ペイジの陣頭指揮によってリマスターされ、加えて公式未発表音源が期待どおりとは言えないにしろ、それなりに大サービス♪ 加えて件のリマスター音源を使用したアナログ盤をセットにする豪華ボックス物までもが出されたのですから、たまりません。
必ずしもゼップ信者ではないサイケおやじにしても、思わずアナログ盤入りの「スーパー・デラックス・エディション」に飛びついての散財は言わずもがな、ところが局地的に「1st」の海外盤2CD仕様、つまり「デラックス・エディション」には隠しトラックが入っているとか、おまけされたライブ音源に別テイク、あるいは別編集バージョンがあるとか、そんな云々が囁かれたのですから、穏やかではありません。
そこでサイケおやじは実際に確認すべく、既に安価安定になっている掲載の輸入盤デジパック仕様の2CD「デラックス・エディション」をゲットし、聴いてみたんですが、結論から言うと、そんな話はデマじゃ〜ないのかっ!?
という散財後悔の物語であります。
しかし、それにしても当時のゼップはパワーありますですねぇ〜〜♪
件の確認作業であるにも関わらず、聴いているうちに冷静さを失っている、そんな前のめりの自分に気がつかされたのがサイケおやじの実相です。
で、まず 「Disc-1」は説明不要、ロック史に屹立するゼップのデビューアルバムと中身は同一ですから、気になるのはリマスターの成果が第一義でしょう。
ただし、そう書きながら、実はサイケおやじはゼップの公式盤CDは、1990年頃に出た4枚組のベスト盤しか持っていないので、安直な比較は出来るはずもないんですが、今では有名な逸話として、アナログ盤とCDでは部分的にミックスが逆チャンネルのステレオパートが混在しているという現実が、ここでもありました。
それと「Dazed And Confused / 幻惑されて」から「Your Time Is Gonna Come / 時が来たりて」と続く曲の流れの繋ぎに、ど〜も不思議な違和感が!?!
等々の点は、あくまでもサイケおやじの主観であって、全体的に大きな変化は無いんじゃ〜ないでしょうか。
なんたって本命はボーナスディスクのライブ音源ですからっ!
そしてこれが熱いんですよ、期待以上に!
しかも録音状態の基本はモノラルミックスながら、団子状に迫ってくる音圧には臨場感がありますし、メンバー各人のパートがきっちり明確というあたりは、これまで夥しく出回ってきたブートとは一線を画するもので、ネタ元になったフランスのラジオ局で放送されたソースから余計なMCをカットしてあるのも高得点♪♪〜♪
もちろん上記の演目はデビューアルバム、そして既にほとんど出来上がっていたと思われる「2nd」アルバムから選ばれていますから、ライブバンドとしての本領発揮は当然が必然ですし、時代を反映(?)してか、曲によってはしっつこいほどの演奏時間の長さは言うまでもありませんが、とにかく初っ端の激しい「Good Times Bad Times 〜 Communication Breakdown」からグッとテンポを落とした「I Can't Quit You Baby / 君から離れられない」へと続く流れは、まさにブルースロックの醍醐味としてツカミはOK!
欲を言えば、「Good Times Bad Times」が例の血沸き肉躍るドラムスのフィルインからイントロのリフだけというのは物足りませんが、荒事丸出しの「Communication Breakdown」のロック魂にはシビレが止まらなくなりますよ♪♪〜♪
う〜ん、このアレンジの上手さっ!
だからこそ、思わせぶりの強い「I Can't Quit You Baby / 君から離れられない」がすんなり楽しめるとしたら、サイケデリックパートが思いっきり引き伸ばされた「Dazed And Confused / 幻惑されて」や起承転結が曖昧になったような「You Shook Me」あたりの超長尺演奏を聴くことは苦行ではなく、むしろイキそうでイケないフラストレーションがカタルシスに導かれる御宣託という事でしょうか。
実際、演奏全篇を通じてロバート・プラントのボーカルは自由度が高く、ドカドカ煩いボンゾのドラミングの中に最高の小技を発見しては目からウロコが落ちまくり、ファンが望むべきところを把握しきったジミー・ペイジの意図的なラフファイトとしか思えないギタープレイにしても、バンドの土台をがっちり支えるジョン・ポール・ジョーンズのベースがあればこそっ!
恥ずかしながら、ここまでジョン・ポール・ジョーンズが上手かったなんて、今頃痛感しているサイケおやじは猛反省です。
また、ジミー・ペイジが親分の威厳を示す「White Summer 〜 Black Mountain Side」ではエレクトリックなラガロックという、この当時ならではの神秘なインド崇拝をやらしていますが、前述したブルース&ハードロックなパートも含めて、ヤードバーズ時代後期のライブ音源と比べれば、相当に練り込まれたステージギグがゼップの所期の目的であったように思ってしまいます。
その意味で新曲扱いであったボンゾのショウケース「Moby Dick」こそ10分近い演奏になってはいるものの、期待の「Heatbreaker」が3分ちょっとなのは些かの肩すかし……。
しかしご安心下さい。
オーラスの「How Many More Times」ではスタジオバージョンから大きく逸脱した展開が凄さの決定版で、しかも未だ公にされていなかった「胸いっぱいの愛を / Whole Lotta Love」の断片が着エロ的に披露されるんですから、たまりません♪♪〜♪
ということで、ロックの歴史云々は別にして、やはりロックが好きになったら、一度は聴いても後悔しないのが、このゼップのデビューアルバムだと思います。
幸いにも、それをサイケおやじは十代で体験出来た事に感謝するばかりですが、これからと決心された皆様であれば、この2CD仕様盤をオススメしたいですねぇ〜〜。
そして最後になりましたが、冒頭に述べた散財仕様の「スーパー・デラックス・エディション」のウリになっていたアナログ盤については、比較対象の私有現役LPがアメリカ盤だけなので安易な事は言えません。と、お断りしたうえで、それでもリマスター音源による新仕様LPは案の定、濁りが取れたような爽やか(?)な仕上がりで、再生装置にも関わる問題かもしれませんが、個人的には「リアルタイムのロックの音」を感じませんでした。
正直、これなら今回出たリマスターCDで十分じゃ〜ないのかなぁ〜〜?
そんな気分なんですよ……。
ただし、それでも気に入っているのは、ベースの鳴り具合がリスマター盤比較でCDよりもLPに軍配! 如何にもの重心の低さに当初からのハードロックの魅力を凝縮する狙いがあったのかもしれません。
もちろん、今となってはアナログ盤の再生装置を備えている音楽ファンは中年者以上が大半でしょうから、こうした「スーパー」というよりも「過剰」な高額商品は、往年を懐かしむタイムマシン、あるいはタイムボックスみたいなもんでしょう。
だとすれば、「時間」を買う事にお金を惜しまない弱みを握られたというか、いやはやなんとも、悲喜こもごも、失礼致しました。